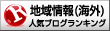実家の土蔵の片づけで大量の廃棄物を出しながら、残すべきものを選んだ。
母親の蔵書とおもわれる一箱を開けたところ、意外な事実が浮かび上がってきた。
母は、歌集を中心とした本を昭和23年に大量に買い込んでいたらしい。

小学校低学年までに両親を失い、親戚を転々としながら、なかば使用人のような暮らし(ある家での食事は台所の板の間で女中さんたちと一緒にとったという)をしていた母は、 小遣いなどもらえるわけもなく、自分の自由になるお金とは無縁だった。
そんななか、短歌に興味をもち、どうにかして勉強はしていたらしい。
戦後まもなく、短歌の会で知り合った父と結婚し、薄給ながら定期収入のある暮らしになったとき、母の短歌欲が爆発したのだろう。
茂吉や白秋はじめ名だたる歌人の作品集のほか、短歌関連の本が20冊あまり。
本の奥付や母が残したメモから、一年のうちに集中的に買い集めたことがわかる。
戦後の混乱期、社会全体が貧しく、わたしの父はその母親ときょうだい3人を結核で次々と失いながら必死に生きていた時代であり、それを伝え聞くわたしは暗いイメージしか抱いていなかった。
ところが今回、おそらく生まれて初めて好きなことにお金を使うことができた母親の弾むような心の足取りが見えてくるようで、日干しにかけた歌集を見ながら暖かい気持ちになることができた。
それとはまったく別の意味で驚いたのは、母の日記だった。
たまたま見つけた一冊は、わたしが4歳のとき(昭和37年)のもので、当時の生活状態がよくわかる。
まず、体が丈夫ではなかった母は、しょっちゅう床についていた。そういう傾向にあったことはわたしも知っていたが、
「今日もからだが重くて何もする気になれず、昼前から午後おそくまで横になる」
といった記述の多さに驚かされた。

また、両親は恋愛結婚だったが、三人目の子育てに必死のこの時期は夫婦関係が難しかったようで、夫の家事への無関心ぶりをなじる言葉が頻出する。
「はらわたが煮えくり返る」
「こんなひとと結婚してしまったのかと思えば・・・」
といったきつい表現がけっこう出てくる。
ストレスから逃れようとしてのことだろう、この時期は台所で酒を口にするキッチンドリンカーをやっていたことが日記には赤裸々に描かれている。
両親もきょうだいもいない天涯孤独の身で、夫への不満を誰にぶちまけることもできなかった母の必死さが伝わってくる。
それではこの頃が「暗黒時代」だったのかといえば、そうでもない部分が散見されて興味深かった。
父は仕事がら日本全国に出かけて家を空けることが多く、それだけでも妻にかける負担の大きさを自覚していたのだろう、子供たちが寝静まったあと、街のレストランへふたりで出かけてコーヒーを飲むシーンがたびたび登場する。
人口数万の地方都市、戦後まもない時期の「レストラン」というのは庶民が着飾って出かける晴れの舞台であり、わたしの郷里には2軒しかなかった。
そこで食事する贅沢は稀なこととしても、一杯のコーヒーで過ごす時間は、父から母への精一杯のプレゼントだったかもしれない。
「でもコーヒーは不味かった」
などと不満を言いながらも、母がレストランについて何度か書き残していることに、子として少し救われる思いがした。
わたしは母と仲が良かったわけではなく、親子の人間関係には大きな問題があったと思っており、彼岸へ見送った今になっても言いたいことはいろいろある。
だが今回、必死になってわたしを育ててくれたことへの感謝とともに、一冊の日記帳をとおして母の歴史に触れられたことはとてもよかったと思っている。
ブログのランキングというのがあって、これをポチしていただくとたいへん励みになります。