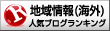東京に長くいたわりには横浜との縁薄く、ちゃんと歩いたことがなかったが、それでも港の見える丘公園ぐらいは来たことがある。
今回も坂をのぼってきて、あたりを散歩してみた。

へえっと思ったのは、この地区の歴史をものがたる展示や説明があちこちにほどこしてあることで、どうやらここ20年ほどのうちに整備が進められたものらしく、わたしよりよほど横浜にくわしい妻が「こんなんなかったでー」を連発していた。
ヨコハマ、都市ブランドにあぐらをかかず、頑張ってるんだね。
わたしは「元町ファッション」なるものがぶいぶいいわせているころに青春時代を過ごしていたが、その聖地である元町へ足を踏み入れたことがなく、このたび初見参となった。

妻が食料品を買い集めてくるのを待つあいだ、見るともなしに路上を眺めていると、東京とはちがう風景がここにあることに気づいた。
フランス車とイタリア車が多いのだ。
東京だったらお金持ちはほぼ間違いなくドイツ車(ベンツ・アウディ・BMW)だが、ここではプジョーだのマセラッティだのといったラテンカーをよく見かけ、その頻度は東京とは比べものにならない。
クルマはおしゃれでなくちゃいけない。ドイツ車乗りたがるのは田舎者。
そんな思いが横浜市民にはあるのかね?
プライド高いという話をよく耳にするが、それはこういうかたちでも出てくるもんなのかね?
余計なことを申し上げれば、ラテンカーはおカネがかかります。
壊れやすさ=維持費用の点で日本車を100点としたとき、
ドイツ車60点、ラテンカー40点以下という感じがします。
その意味ではラテンカーの所有はガチで気合の入ったファッション行為なんでありますね。
痩せ我慢してでもオシャレに、というのがハマのプライド?
独断と偏見の人間観察をふくめ、元町界隈はたいへん人間的で好ましいところだった。
一方でわたしたちが宿泊した「ベイエリア」はちっとも好きになれなかった。

再開発により整然と組み立てられたこの地区は、役所やデベロッパーが都市効率を追い求めるばかり、人間くささがほとんど感じられない冷たい箱庭のようになってしまった。
人間くささというのは、スローで無駄な細部から立ちのぼってくる味わいであり、ここにはそれがない。
この地区には、公園や遊園地など大掛かりなエンタテインメントが多数埋め込まれているにもかかわらず、人間くささどころか、逆に「ハイみなさん設計どおりに行動してください」と言われているようで、歩けば歩くほどしらけてしまう。
というふうに抽象的な説明にしかならないので、あとはみなさん自分の足で感じてみてください。
自分、少数派ってことはわかってます。
この地区に、圧倒的に人間くさい施設がひとつあった。
海外移住資料館といい、明治から昭和にかけてハワイ・北米・南米に進出していった「日系人」の足跡をたどる展示がしてあった。

すごく意外だったのは、初期のハワイ移民が明治政府による選抜で行われていたこと。
当時のハワイ王(カメハメハ4世)から移民の要請をうけた日本政府は、良質な労働力を責任をもって送りだすべく、移民希望者の選抜を行った。
働き者であることはもちろん、海外の厳しい環境にめげずに頑張れる人材という観点で選んだ結果、移民の大半を熊本・大分・広島・福島出身者が占めることになり、なかでも広島からの移民が圧倒的に多かったという。
いろんな意味ですごい時代だよね。
ひとつ胸が痛んだのは、北海道のこと。北海道民は政府による選抜からは漏れたが、その後の長い移民史のなかでどんどん存在感を増していく。
移民を希望する最大の理由は貧しさだが、そもそも北海道民の多くが明治になって本州から入植し、さんざんに苦労を重ねてきたひとたち。
それでも貧しさから逃れることができず、すべてを捨てて海外に賭けようとしたのだから、その決心は悲痛というほかない。
わたしたちは明治以降の日本人が順調に豊かになってきたかのような錯覚をしがちだけれど、事実はかなり違うはずだ。
ベンツもプジョーもいいけれど、それって奇跡のような豊かさじゃないか、「あの貧しさ」は実はそんなに遠くに行っておらず、振り向けばわたしたちの背中にぺたりと貼りついているんじゃないかと、そんなふうに思ってみたりするヨコハマベイエリア散策なのであった。
ブログのランキングというのがあって、これをポチしていただくとたいへん励みになります。