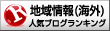母親の死を見送った。
時節がら、一族のうち遠隔地にいるものは帰省しないという取り決めにしたがい、パソコン越しに見守った。
心拍数が60から45、そして20へと下がり、ゼロになった。
東京の甥っ子が顔をくしゃくしゃにした。
しばらく見ないうちにえらく額が後退している。
義兄は髪が真っ白。日本時間は午前3時だから、寝ているところを叩き起こされたのだろう。
このひとも老けたなあ。だけどみんなも俺を見てそう思っているんだろう。
それにしても機械のピーピー音がうるさい。すぐに止められるものでもないのだろうが・・・
小さな画面の隅で動かなくなった母の姿を見ながら、そんなことをぼんやり考えていた。
父親を病床で見送ったときとちがい、気持ちの置きどころがない感じ。
こういうかたちでしか見送れないことがわかっていたからイメージトレーニングのようなことをしてきたけれど、なんの役にも立たなかった。
母が息を引き取ったという事実が宙に浮いており、それをわたしがぼんやりと眺めている。
母は誰よりもイヌが好きだったのに、決して飼おうとはしなかった。
若いとき、末息子のわたしに物心がつく前、うちではサンタという名のイヌを飼っており、母はたいへん可愛がったという。
サンタが死に、その悲しさに耐えられなかった母は、二度とイヌは飼うまいと決心したらしい。
以上は姉から聞いた話で、母本人はこのことを心に封印している様子だった。
ただイヌ好きは生涯かわることなく、「おともだちに会いにいってくる」といって散歩に出かけては、床屋のドアを半開きにしてシーズーのココちゃんに挨拶し、結納品屋の勝手口に入り込みボーダーコリーのリンちゃんを呼び出してわしゃわしゃし、その他大勢のわんこたちに挨拶してまわるのが日課だった。
晩年、大きな不幸に見舞われたせいで活力を失った母に、今こそイヌを飼ってもらいたかったが、まったく取り合ってもらえなかった。
まだ日本にいたわたしたちが、もしもイヌを飼っていたなら、時間をみつけては帰省し、母にわんことすごす幸せを再発見してもらうことができたかもしれない。
だが当時わたしたちは脱サラ渡米を予定しており、イヌを飼うわけにはいかなかった。
母がイヌとの縁をとりもどすことなく人生を終えたことに、罪悪感のようなものがうっすらと残った。
なんの話をしているのだろう。
気持ちに整理をつけていくのはこれから。
ひとついえることは、わたしのイヌ好きは遺伝によるものであり、これを受け継げたことはたいへん有難かった。
というか動物にやさしくいられることは数少ない自分の誇りかな。

郷里では最低限の通夜と葬儀を予定しており、名目上の喪主であるわたしはリモートで参加することになる。
ブログのランキングというのがあって、これをポチしていただくとたいへん励みになります。